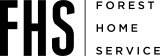燃料価格の高騰などを受けて「電気料金が高くなった」と感じている方も多いのではないでしょうか。2023年11月、大手電力会社10社は、2024年1月からの電気料金を発表し、東京電力も値上げする見通しです。
今後も電気料金が安定する見込みが立たない今、「太陽光発電設備を自宅に導入する」という選択肢が注目を集めています。そこで本記事では、東京都にお住まいの方向けに太陽光発電の補助金制度について、詳しく解説いたします。この記事を参考に、どの制度が活用できるかをしっかりとチェックし、補助金の利用を検討してみてください。
補助金の仕組みと目的

太陽光発電システムの導入に向けた補助金は、全国の自治体や国でも行われています。しかし、国の住宅用太陽光発電向け補助金は、2013年3月31日に一度終了し、現在では法人・企業などの事業者向けの補助制度が残るのみとなっています。とはいえ、都道府県や市区町村によっては太陽光発電設備への助成金が充実しており、複数の制度を併用できる場合もあります。
ここでは、東京都が定める代表的な補助金制度をご紹介します。
東京都の太陽光補助金の概要
東京都が定めている太陽光補助金は、大きく分けて「東京ゼロエミ住宅導入促進事業」と「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」の2つがあります。
ここでは、それぞれの補助事業について詳しくご紹介します。
東京ゼロエミ住宅導入促進事業
「東京ゼロエミ住宅」とは、「高い断熱性能の断熱材や窓を用いたり、省エネ性能の高い照明やエアコンなどを取り入れた、人にも地球環境にもやさしい都独自の住宅」のことです。具体的には、高効率のエアコンや、LED照明、高断熱窓・ドア、高断熱浴槽、高効率給湯器などを備えた住宅を指します。
令和5年度は約241億円の予算が設けられており、令和4年度の約159億円に比べ、約1.5倍に拡大しています。予算に対する申請状況(割合)は、「(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)」のHPで公開しており、誰でも見ることが可能です。
以下では、東京ゼロエミ住宅導入促進事業の概要をご紹介します。
助成対象者
新築住宅の建築主(個人・事業者)、太陽光発電設備・蓄電池及びV2Hのリース事業者
助成対象住宅
- 「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」に基づき、「東京ゼロエミ住宅」の認証を受けた都内の新築住宅(戸建住宅・集合住宅等)
- 床面積の合計が 2,000平方メートル未満であること
申請期間
令和5年4月3日~令和6年3月29日(令和5年度の場合)
助成金額
| 水準1 | 水準2 | 水準3 | |
|---|---|---|---|
| 戸建住宅 | 30万円/戸 | 50万円/戸 | 210万円/戸 |
| 集合住宅等 | 20万円/戸 | 40万円/戸 | 170万円/戸 |
対象住宅に設置する太陽光発電設備、蓄電池、V2H機器等の補助は、以下の通りです。
| 対象機器 | 助成金額 | 上限額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 3.6kW以下 | オール電化住宅 | 13万円/kW | 39万円/棟 |
| オール電化以外の住宅 | 12万円/kW | 36万円/棟 | ||
| 3.6kW超 50kW未満 | オール電化住宅 | 11万円/kW | (50kW以上は対象外) | |
| オール電化以外の住宅 | 10万円/kW | |||
| ●小型であるなどの東京の地域特性に対応した機能を有する製品(機能性PV)を対象に、1kW あたり5万円(又は2万円)を加算 | ||||
| ●陸屋根形状のマンション等に架台を用いて設置する場合は、架台の設置経費を対象に、1kWあたり20万円を上限として加算する。 | ||||
| 蓄電池 | 蓄電池を単独で設置する場合 | 機器費、材料費及び工事費の3/4 ※ただし、蓄電池システムの機器費が蓄電容量 1kWh当たり 20 万円以下であること | 15万円/kWh かつ 120万円/戸 | |
| 4kW以下の太陽光発電設備とともに設置する場合 | ||||
| 4kW超の太陽光発電設備とともに設置する場合 | 15万円/kWh かつ太陽光発電出力×30万円/戸 | |||
| ●蓄電池の蓄電容量の合計が6.34kWh未満の場合、上限額を19万円/kWhかつ95万円/戸とする。 | ||||
| V2H | 機器費等の1/2(上限額50万円) | |||
| ※電気自動車(EV)等を所有し、太陽光発電設備を設置している場合は100%助成 (上限額100万円) | ||||
問い合わせ先
創エネ支援チーム 東京ゼロエミ住宅促進事業担当
電話:03-5990-5169
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業
「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」は、省エネ性に優れ、災害にも強く、健康にも資する断熱・太陽光住宅の普及拡大を促進する目的で導入された制度です。
太陽光発電設備はもちろん、高断熱窓・ドア、外壁等の断熱施工、V2H、蓄電池システム、太陽熱利用システム、地中熱利用システム、エコキュートなど、さまざまな省エネ・再エネ対策に対応しています。
令和5年度の予算は496億円と、令和4年度の409億円よりも約20%も拡大しています。
以下では、太陽光発電設備および蓄電池システムの補助に関する概要をご紹介します。
助成対象者
■太陽光発電設備
- 助成対象機器の所有者又は管理組合
- 助成対象機器をリース等により個人に対して貸与する者
■蓄電池システム
助成対象機器の所有者(国、地方公共団体は除く)
助成対象住宅
■太陽光発電設備
都内の新築または既存住宅
■蓄電池システム
太陽光発電設備と併せて蓄電池を設置する、または既に太陽光発電設備を導入している住宅
申請期間
■太陽光発電設備
令和9年度まで(助成金の交付は令和11年度まで)
令和5年度申請期間:令和5年6月30日~令和6年3月29日まで
■蓄電池システム
事前申込:令和5年5月29日~
交付申請兼実績報告:令和5年6月30日~令和10年3月31日(17時公社必着)まで
助成金額
■太陽光発電設備
| 助成対象機器 | 補助金額 | |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 新築住宅 | (1)3.6kW以下の場合]…12万円/kW(上限36万円) (2)3.6kWを超える場合…10万円/kW(50kW未満) ※但し太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする |
| 既存住宅 | (1)戸建(陸屋根)の場合…10万円/kW (2)集合住宅(陸屋根)の場合…20万円/kW ※架台の材料費及び工事費の合計金額を上限とする |
また、太陽光発電設備の設置にかかる経費のうち、以下については上乗せで補助する制度もあります。
| 助成対象 | 上限額 | 要件 |
|---|---|---|
| 防水工事 | 上限18万円/kW (既存集合住宅及び既存戸建住宅) | 陸屋根の既存住宅に太陽光発電システムを設置する際に行ったもの 等 |
| 架台設置 | (集合住宅)上限20万円/kW (既存戸建住宅)上限10万円/kW | 陸屋根の住宅に太陽光発電システムを設置するもの 等 |
| 機能性PV | 上限5万円(又は2万円)/kW | 優れた機能性を有する太陽光発電システムとして認定された製品を設置するもの等 |
■蓄電池システム
| 助成対象 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 蓄電池システム | 3/4 | ■太陽光(4kW以上)と蓄電池を併せて設置の場合 以下のうちいずれか小さい額(最大1,500万円) (a)蓄電池容量:15万円/kWh(100kWh未満)(※) (b)太陽光発電設備容量:30万円/kW |
| ■太陽光(4kW未満)と蓄電池を併せて設置又は蓄電池のみを設置の場合 15万円/kWh(※)、最大120万円/戸 | ||
| (※)5kWh未満の場合は19万円/kWh (5kWh以上6.34kWh未満の場合は一律95万円) |
問い合わせ先
■太陽光発電導入関連
温暖化対策推進課 創エネ支援チーム 太陽光担当
電話:03-6659-3420
■蓄電池関連
スマートエネルギー都市推進担当 蓄電池ヘルプデスク
電話:03-6258-1510
補助金の背後にある理念
上記のような補助金制度を設けているのは、東京都が2050年までに世界のCO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」の実現を目指しているためです。都は、2030年までに温室効果ガス排出量を2000年比で50%削減する「カーボンハーフ」に向けた取り組みを加速させています。都内の温室効果ガスは約30%が家庭から排出されており、住宅の省エネ性能を高めることは、こうした目標を達成するために欠かせません。
しかし、都内は土地の狭さや建設費の高さから、上記のような取り組みが進みにくいという背景があります。こうした問題を解決するため、一定の水準をクリアした「東京ゼロエミ住宅」を普及させ、環境性能の良い住宅を選択できるようにする狙いがあるのです。
また、「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」は新築だけでなく、既存住宅のリフォームに対しても、補助金を交付しています。
補助金申請から設置までの手続きと注意点

東京都が提示している補助金申請は、オンライン申請と郵送の2種類の申請方法があります。2022年度は交付申請・実績報告の2段階申請が必要でしたが、2023年度からは簡易な事前申請さえしていれば、実績報告と交付申請を同時に行い、1回の申請で完了できるようになりました。ただし、申請から設置に至るまでは審査基準、提出する書類、守らなければならない手順など、注意点がいくつかあります。
ここでは、申請の流れやスムーズに申請するために必要なポイントをご紹介します。
補助金申請の手続きと期間を確認
東京都の太陽光関連の補助金は、東京都環境公社が開設する「クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)」に申請します。
「ゼロエミ住宅」や「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」など、制度によって申請できる期間が決まっているため、必ず期限内に申請しましょう。ただし、申請総額が予算に達した時点で受付は終了するため、できるだけ早く申請するのをおすすめします。
審査基準を確認
太陽光発電設備を導入する際は、ハウスメーカーなどの事業者から事前に見積もりを出してもらうケースがほとんどです。その際、対象の発電容量などをしっかりとチェックし、補助金の基準を満たしているか確認しましょう。また、ソーラーパネルや蓄電池は、国の基準や認定を受けているメーカーのみが補助対象となるため、関連業者には補助金を利用することを必ず伝えておきましょう。
その他にも、区や市の補助金制度の場合、「住民税を滞納していない」などの条件が設定されていることが多いため、こちらも注意が必要です。
必要書類と申請の流れを確認
補助金の種類によっては、業者などが申請を代行するケースもありますが、ここでは自分自身で申請する場合の流れや、必要書類を解説します。
1.業者に見積もりを依頼する
太陽光発電設備の導入には、まず太陽光発電パネルのメーカーや設置業者などへ見積もりをお願いする必要があります。メーカーや業者ごとに費用が異なるため、自分に合ったものを選びましょう。
2.事前申し込みを行う
クール・ネット東京のサイトより、メールアドレスを登録し、事前申し込みフォームから申請者名、住所、設備などの情報を記入し、事前申し込みを完了させます。
この時、業者から受け取った見積書(PDFファイル)を添付しましょう。電子申請の場合、数分で受付通知がメールで届きます。
3.業者と契約・施工をスタート
1で見積もりを出してもらった業者と正式に契約します。事前申し込みの完了前に契約してしまうと、補助金の対象外となるケースがあるため、注意しましょう。補助要件の審査は工事完了後に行われるため、補助要件を十分に確認した上で設置・工事を行いましょう。
4.交付申請・実績報告
施工が完了次第、補助金の交付申請と実績報告を行います。申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 太陽光発電システム設置概要書
- 助成申請者本人確認書類
- 助成申請者実在証明書類(法人の場合のみ)
- 登記事項証明書
- 設置に係る決議書またはこれに代わるもの(集合住宅の共用部設置の場合のみ)
- 太陽光発電システムの設置に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 対象機器を購入した際の領収書の写し及び領収書の内訳書
- 保証書関連書類
- 『接続契約のご案内』等
- 建物および土地の全景写真
- 陸屋根の架台設置・架台設置に伴う防水工事の写真
- モジュール設置完了後の写真
- モジュールの割付図
- 機能性 PV の上乗せがある場合の必要書類
- リース等契約証明書(リースの場合)
- 重要事項説明書
- 国及び他の地方公共団体による補助金の交付額確定通知書の写し ほか
こうした書類は、いざ施工が完了してから用意すると時間がかかってしまいます。そのため、有効期限等を確認しながら、着工前に少しずつ用意しておくと良いでしょう。
5.審査~助成金交付通知書の送付
申請後は、書類不備がないかどうか、要件に当てはまるかどうかなどの審査が入ります。問題なければ交付決定通知書が届きます。申請~交付決定通知書が届くまではおよそ2~3カ月程度、実績報告書の受付から5カ月程度で助成金確定通知書が届きます。
助成金の確定通知後、指定口座への振込みまでは約3週間かかります。余裕をもって申請し、「入金が遅い……」と焦ることのないようにしましょう。
太陽光発電システムの設置と市区町村の支援
上記で紹介したのは、東京都の財源から補助される制度です。しかし、都内では市区町村が主体となって太陽光発電設備についての補助金を出しているところもあります。
以下では、いくつか代表的な例をご紹介します。
江東区 地球温暖化防止設備導入助成
江東区は、地球温暖化防止のため、区内に太陽光発電や省エネルギー設備等を導入する個人・事業者・管理組合等を対象に、設置費用の一部を助成しています。
個人住宅だけでなく、集合住宅も補助対象に入っており、太陽光パネルだけでなく蓄電池やHEMS、エコキュート、エネファームなどにも活用できる制度です。
| 補助対象設備 | 助成金額・補助率 | 要件 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 最大出力に応じ、5万円/kW(上限20万円) ※個人住宅で蓄電池と同時申請する場合、6万円/kW(上限24万円) | モジュールの公称最大出力の合計値が10kW未満のもの(ただし、集合住宅の場合は10kW以上も対象) |
| 蓄電池 | 蓄電池容量に応じ、1万円/kWh(個人宅:上限10万円 集合住宅:上限50万円) ※個人住宅で太陽光発電と同時申請する場合、2万5000円/kW(上限20万円) | 太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池装置(エネファーム)と常時接続していること |
| エネルギー管理システム機器(HEMS・MEMS) | 設置に要する経費の5%(個人住宅:上限2万円 集合住宅:上限15万円) | – |
| CO2冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 設置に要する経費の5%(上限4万円) | 集合住宅は対象外 |
| 家庭用燃料電池装置(エネファーム) | 設置に要する経費の5%(上限10万円) | 集合住宅は対象外 |
| 高反射率塗装 | 施工面積1平方メートルあたり1,000円を乗じた額(個人住宅:上限20万円 集合住宅:上限150万円) | 施工面積は、小数点第3位以下切り捨て |
| 高断熱窓 | 設置に要する経費の10%(個人住宅:上限10万円 集合住宅:上限100万円) | 新築は対象外 |
| LED照明(集合住宅の共用部分のみ) | 設置に要する経費の10%(上限額:50万円) | 新築・新規設置は対象外 |
| 電気自動車等充電設備 | 設置に要する経費の10%(普通充電設備:1基あたり上限10万円 急速充電設備:1基あたり上限50万円) | 1回の申請につき普通充電設備5基まで、急速充電設備1基まで |
品川区 太陽光発電システム設置助成事業
品川区は、再生可能エネルギーの導入促進を目的として、太陽光発電システムおよび蓄電池システムを設置する経費の一部を助成しています。
家庭用・業務用問わず申請可能ですが、予算がなくなり次第終了するため、注意が必要です。
| 補助対象設備 | 助成金額 |
|---|---|
| 太陽光発電システム | 3万円/kW(上限9万円) |
| 蓄電池システム | 1万円/kW(上限5万円) |
補助金の活用事例と環境への貢献

■都内木造3階建て住宅(戸建)の場合
| 建築費用 | 5000万円台 |
| 助成金 | 254万円(建物全体:210万円 太陽光発電44万円) |
| 主な設備 | 太陽光パネル(4.4kW) 空調:壁掛けエアコン(5.6kW)2台 給湯:エコキュート 照明:全室LED 断熱:屋根断熱、壁断熱、床断熱、基礎断熱、窓、玄関ドアなど |
| 一次エネルギー消費量(年間) | 79196MJ(40%削減) |
こちらのケースでは、敷地面積が100平方メートルほどと太陽光発電設備の搭載量が限られることが課題でした。しかし、屋根南面の面積を最大化し、都の助成金を用いて太陽光パネルを設置することで、大幅な一次エネルギー消費量の削減が可能になりました。屋根、床、壁、基礎など、断熱性を高くしたことで冷暖房負荷も大きく軽減されました。
設置のメリット
いくつかの条件はあるものの、東京都で太陽光発電システムを導入することは大きなメリットがあります。
ここでは、太陽光発電設備のメリットをご紹介します。
メリット1:電気代が節約できる
自宅に太陽光発電システムを設置すると、発電した電力を自家消費できます。こうしてできた電力は無料で使えるため、電気料金が大幅に節約できるのが最大のメリットです。
また、一般的な電力会社のプランである「従量電灯」は、電気の使用量が多ければ多いほど、単価が高くなる仕組みです。自家消費する電力が増え、電力会社から購入する電力が減れば、さらなる電気代節約が見込めます。
世界的な燃料費の高騰により、電気代の値上がりが続いている今、太陽光発電を導入するメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
メリット2:環境にやさしく、CO2排出量が抑えられる
日本の電力は、化石燃料による「火力発電」が全体の73.1%を占めています。太陽光発電は、火力発電と異なり二酸化炭素や温室効果ガスが発生しないため、地球にやさしいクリーンなエネルギーと言えます。国は、気候変動などの世界的な環境課題に取り組むべく、持続可能な開発目標(SDGs)として再生可能エネルギーの利用を推進しています。
こうした取り組みに参加することによって、企業であれば環境に配慮したサステナブルな経営を実現しているという評価を得られます。個人であっても、環境に対する意識が高まり、節電などを強く意識するようになったという声も多いようです。
メリット3:災害などの緊急時にも安心
地震や洪水など、思いもよらない非常事態であっても、ソーラーパネルや蓄電池といった設備を導入していれば、非常用電源として利用できます。災害時にテレビやスマートフォンによる情報収集や、炊飯器などによる調理ができるのは大きなメリットとなります。
蓄電池で昼間の間に電力を充電しておけば、夜の間も電気が使えるため、在宅避難の際も安心して過ごせるでしょう。
メリット4:売電収入を得られる場合も
太陽光発電設備を設置すると、電気料金を節約できるだけでなく、余った電気を電力会社へ売ることができます。蓄電池があれば日中に発電した電力を貯めておけますが、蓄電池がない場合でも電力会社に買い取ってもらえます。
2023年度の住宅用太陽光発電設備(容量10kW未満)の売電収入は、1kWhあたり16円です。FIT制度(固定価格買取制度)」により、10年間は固定価格での買取りが保証されており、定期的な売電収入が見込めます。
設置のデメリット
導入前にはメリットだけでなくデメリットもしっかりと把握しておくことが後悔しないための秘訣です。
ここではデメリットをご紹介します。
デメリット1:初期費用がかかる
太陽光発電設備の導入において、最も大きなデメリットは設置費用などの初期費用がかかることです。2022年12月に発表された経済産業省のデータによると、2022年に設置された新築住宅の太陽光発電システムの初期費用は、平均は26.1万円/kWという結果が出ています。一般的な住宅用太陽光パネルの設置容量は3kW~5kWと言われているため、平均の通りであれば78.3万円~130.5万円の初期費用がかかる計算です。
初期費用は年々減少傾向にあるものの、決して少なくない出費となるため、大きなハードルになることは間違いありません。各自治体などの補助金を活用しても100%の補助はありませんので、ある程度まとまった額が必要となります。
デメリット2:発電量が安定しない
太陽光発電は、その名の通り太陽光が発電用パネルに当たることで電力を生み出す仕組みです。そのため、曇りや雨、雪などの悪天候時には十分な発電ができないのがデメリットといえます。また、夏は日が長く、発電量が多くなる一方で、冬は日が落ちるのが早く、夏に比べて発電量が減少します。
日々の発電量が安定しないとはいえ、年間を通しての発電量は大きく変動することはないため、短期的なメリットを求めるのではなく、年単位の長期的な視点を持つことが大切です。
デメリット3:定期的なメンテナンスが必要
太陽光発電パネルは、多くは屋根の上に設置されるため、雨や風、台風、塩害といった自然現象による故障や劣化のリスクを伴います。そのため、定期的なメンテナンスや修理が必要です。
設置業者やパネルのメーカーを選ぶ際には、アフターメンテナンスや保証期間もしっかりと考える必要があります。太陽光パネルだけでなく、パワーコンディショナーなどの寿命もあるため、交換費用も念頭に置きながらコスト計算をしましょう。
デメリット4:設置に適さない場合もある
住宅に太陽光パネルを設置する場合、屋根の上などに設置する場合がほとんどです。新築住宅であれば、あらかじめ設置に適した形状の屋根にすることも可能ですが、既に建っている住宅に太陽光発電設備を設置する場合は、屋根の形状や傾斜の方角、日照量の関係で、設置に適さない場合があります。
まずは専門の業者による現地調査を通し、発電のシミュレーションをしっかりと行うことが大切です。
まとめ

東京都の太陽光発電補助金制度は、ソーラーパネルだけでなく、対象設備が多いのが特徴です。これから都内に家を建てる人はもちろん、家のリフォームを考えている人も補助対象になる可能性があるため、まずは制度についての理解を深めることが大切です。
また、東京都はハウスメーカーなどに対し、新設住宅への太陽光発電設置を2025年4月から義務化する制度を発表しています。こうした背景もあり、令和6年度以降は補助金制度が変更される可能性があるため、詳細は関連ホームページなどをこまめにチェックしましょう。