今、日本は国をあげて電気自動車(EV)の普及に力を注いでいます。
経済産業省の発表によると、日本政府は「2035年までに新車販売の電動車(※)率を100%にする」という目標を掲げ、「公共用の急速充電器3万基を含む充電インフラ15万基を設置し、2030年までにガソリン車並みの利便性を実現」という計画を打ち出しました。
こうした国の後押しをはじめ、環境意識の高まりや、SDGs(持続可能な開発目標)の推進により、今後もいっそうEVの普及が進むと予想されます。
さて、そんな社会の動きの中で、国内外のEVの普及は、現在どの程度進んでいるのでしょうか。
この記事では、EVの普及率や、これまでの歴史、今後の見通しなどについて解説します。
※「電気自動車(EV)」だけでなく、「燃料電池自動車(FCV)」「プラグインハイブリッド自動車(PHV)」「ハイブリッド自動車(HV)」を含む
日本と世界の電気自動車(EV)の現状と普及率
の普及率は?これまでの歴史と今後の見通し_01-1024x538.png)
2015年の「パリ協定」の採択以降、カーボンニュートラルの実現に向け、CO2排出量が削減できる電気自動車(EV)の普及が世界各地で進んでいます。
まずは、日本と世界各国におけるEVの「今」を見ていきましょう。
日本の普及率
一般社団法人日本自動車販売協会連合会の統計によると、2021年1月〜12月のEV普通乗用車の販売台数は2万1,139台。全体の販売台数の約0.9%を占めています。
翌2022年1月〜12月のEV普通乗用車の販売台数は3万1,592台と、前年比1.5倍の増加となりました。全体の販売台数の約1.4%を占めています。
ただし、これらの数字データは「普通自動車」に限定したものであり、軽自動車は含まれていません。
ここで注目すべきは、2022年5月20日に発売された日産「サクラ」、三菱「eKクロスEV」という2台の軽EVです。「200万円台でEVが買える」というコストパフォーマンスの良さから、ガソリン車から乗り換えしたユーザーも続出しました。
実際、日産「サクラ」は、2022年6月の発売から12月までの半年間で売上台数2万1,887台という数字を叩き出しました。三菱「eKクロスEV」は同様に4,175台を売り上げ、2種合わせて軽EV車の2022年の売上台数は2万6,062台に上ります。この数字は、2022年のEV普通乗用車販売台数の約82%の数字に当たります。
こうした背景から、2022年は「EV元年」とも呼ばれ、上記2台は2022-2023 日本カー・オブ・ザ・イヤーにも選ばれるなど、EV軽自動車への注目も高まっています。
急速な普及率アップのもう一つの要因として考えられるのは、政府による補助金の拡大です。
日本政府は「2035年までに、乗用車の新車販売で電動車率100%を目指す」という目標の実現を目指し、EV・PHV・FCVを対象に、購入補助制度を設けています。
2022年度においては予算額を約700億円に拡充し、補助上限額が大幅に引き上げられました。EVの例を挙げると、これまで補助上限額は40万円でしたが、最大85万円にまで増額しています。
さらに、2022年は世界的な半導体不足により購入希望者への納車が遅れていたという背景もあり、2023年はますますEVの普及が進む見込みです。
世界の普及率
日本のEV普通乗用車の普及率は1.4%と、急速に拡大しているとはいえ、まだまだ少ないのが現状です。
一方で世界各国、特に欧米諸国や中国はEV市場の成長が顕著であり、販売台数も飛躍的に増加しています。
ここでは、国別のEVの普及率や、その背景にある政策などをチェックしていきましょう。
中国
中国汽車工業協会が2023年1月に行った発表によると、2022年の新車販売台数は前年比2.1%増の2686万4000台に上りました。このうち、EVは前年比81.6%増の536万5000台となり、全体の約20%の割合を占めます。
中国では、EVに加えてPHEV(プラグインハイブリッド自動車)やFCV(燃料電池自動車)を加えたものを「NEV(New Energy Vehicle=新エネルギー車)」と呼び、分類しています。
中国政府はこのNEV普及率を2025年までに25%まで引き上げるという目標を掲げており、その対策として自動車メーカーへ販売台数の一定割合をNEVにすることを義務付ける「NEV規制」を実施しました。
そして、2022年のNEV販売台数は688万7000台と過去最高を記録し、新車市場に占めるNEVの比率は25.6%という圧倒的な数字を記録しました。
結果として、「NEV普及率25%」という目標を3年前倒しで達成した形となります。
規制が始まる以前の2018年は、新車販売台数に占めるEVの割合が4%にとどまっていたことを考えると、他に類を見ないほどのスピードで普及していると言えるでしょう。
アメリカ
アメリカの2022年度の新車販売台数は、10年ぶりに過去最低を記録し、1,390万台にとどまりました。一方、このうちEV(BEV、PHEV)と燃料電池車(FCV)の販売台数は94万台を占め、全体の6.7%という数字を記録しています。これは、2021年の4.1%という数字から2.6ポイントも増えていることになります。
中でもバッテリー式電気自動車(BEV)は前年度比65.3%増と圧倒的なシェアを記録しました。特に「テスラ」のBEVは52万2,444台を売り上げるなど、全メーカーのBEVの6割を占めています。
日本とは比較にならないほどのスピードでEV普及が進んでいる理由は、国を挙げての多様な取り組みがあるからです。
まず、バイデン政権は2030年までにアメリカ国内のEVの販売台数を50%まで引き上げるほか、全米に50万台のEV用充電器を設置する目標を掲げています。
実際に2021年に可決された「インフラ投資計画法案」では、全国のEV充電施設整備などに150億ドルの予算を充てることが決められました。
また、「EV充電プログラム(NEVIフォーミュラプログラム)」として2022年〜2026年度の5年間で、州間高速道路への充電施設の設置に50億ドルの助成金が充てられることになりました。これは、EVが州間をまたいで全米へと行き来しやすくすることで、EVの普及率アップにつなげる狙いがあります。
しかし現在、アメリカの充電ステーションは約4万8000カ所にとどまり、ガソリンスタンドの15万カ所に比べると、はるかに数が足りていない状況です。
そんな中、環境への意識の高いカリフォルニア州では、2035年までに州内でのガソリン車の販売を禁止する計画を承認するなど、独自の取り組みも広がっています。
ノルウェー
世界で最もEVが普及している国として有名なのが、北欧に位置するノルウェーです。
2021年の新車販売台数のうち、64.5%をEVが占め、プラグインハイブリッド車(PHV)も21.7%という高い数字を記録しました。
2020年のEVシェア率は54%だったため、わずか1年で10%も上昇したということになります。
ノルウェーでは、2025年までに新車のガソリン車・ディーゼル車を販売禁止することを目標とし、実現に向けて着実に成果をあげています。
また、ノルウェーはEV普及に向けていち早く取り組みをスタートさせた国としても知られ、1990年には最初の購入税及び関税の免除による優遇措置が導入されました。その他にも、エンジン車には25%もの購入税、付加価値税を課し、EVはそれらをゼロにするなどの優遇策が大きな効果を上げています。加えて、ガソリン車からEVに乗り換える際は日本円にして100万円単位で補助金が支給されたり、高速道路の通行料が割引されるなど、積極的なEV政策がとられています。
さらに、充電インフラの整備にも多額の予算が充てられており、公共の充電ステーションが市街地や高速道路などに広く設置されています。
こうした政策があったとはいえ、なぜここまでEVが普及したのでしょうか?
それは、国そのものの特徴に理由があります。
寒冷地であるノルウェーでは、冬場はガソリンのオイルが凍結する場合があり、家庭用・公共に関わらず駐車場には電源設備が整っていることが一般的でした。その設備をEVの充電ステーションへ転用したため、普及スピードが速かったという点が挙げられます。
また、ノルウェーは豊かな自然を活かして電力の96%を水力発電でまかなっており、再生エネルギーが創出されやすい環境だったことも起因しています。
フランス
フランスの2022年上半期(1~6月)におけるEV・PHV自動車販売シェアは、20.2%となっており、ヨーロッパの中でもトップクラスの普及率を誇っています。
2020年6月に「低公害車購入支援措置」を導入し、4万5,000ユーロ以下のEVを購入またはリース契約した場合、個人向けに7,000ユーロ、企業向けに5,000ユーロを支給するなどの補助金制度をスタートさせました。
この補助金制度は、後に対象をプラグインハイブリッド車(PHEV)にまで広げたこともあり、同年のPHEVの販売台数は前年度の約4倍にまで膨らみました。
マクロン大統領はこの他にも、公共のEV充電器の設置数を2023年6月までに10万カ所に増やす計画を立て、2023年5月5日には10万カ所に到達したと発表しました。
さらに、2027年には新車販売台数の30%をEVが占めるという見通しが立てられています。
フランスでは2040年までに、ガソリン車・ディーゼル車の新車販売を禁止する方針を示し、首都であるパリはこれに先駆けて2030年までに禁止するという目標を掲げています。
なぜパリが先んじてこうした目標を設定しているのでしょうか?
その理由は、パリ住民の約6割が車を持っていませんが、それ以外の地域では圧倒的な「車社会」だという背景があります。車が欠かせないパリ以外の地域には余裕を持たせ、母数の少ないパリでのEV買い替えを積極的に促進する狙いがあるようです。
電気自動車(EV)の歴史
の普及率は?これまでの歴史と今後の見通し_02-1024x538.png)
電気自動車(EV)の歴史は古く、19世紀には既に試作車が登場していました。
最初のガソリン自動車は1885年、ドイツのダイムラーとベンツによって発明されました。しかしその10年以上も前の1873年には、イギリスのダビットソンにより、初めてEVが作られていたのです。
1900年頃のアメリカでは、自動車の生産台数の4割がEVという数字データがあり、ニューヨークのタクシーはすべてEVだったとも言われています。
このように、EVが主力として活躍していた時期もありましたが、1909年には大量生産車の代名詞であるT型フォードが誕生し、ガソリン自動車が瞬く間に広がっていきました。一方、EVは走行距離が思うように伸びず、1930年代には姿を消していったのです。
1947年には、日本初のEVである「たま電気自動車」が作られ、最高速度35.2 km/h、航続距離96.3 kmという高性能ぶりが注目を集めました。
そんな新しい時代の予感も束の間、1950年代には電池の材料である鉛の価格が高騰したことや、道路運送車両法から「電気自動車」の項目が削除されたことが打撃となり、またしても影を潜めてしまいます。
1960年代の世界的な環境汚染や、1973年のオイルショックによるガソリン価格の高騰により、再びEVへ光が当たります。しかし、ガソリン代の価格が落ち着くにつれて再び姿を消す……ということが、何度も繰り返されました。
その裏で、世間は環境にやさしい、いわゆる「エコ」な自動車への興味・関心を募らせていきました。1990年にはアメリカ・カリフォルニア州で新車販売台数の内2%をEVとするZEV(Zero Emisshon Vehicle)法が持ちあがり、メーカー各社はEVの研究・開発へと没頭していきました。
世界が新たな方向へ動き出す中で、1997年に「トヨタ・プリウス」が生まれました。「21世紀に間に合いました。」というキャッチフレーズはその当時の空気感を象徴しており、インパクトがありますね。
プリウスの登場により、「環境性能でクルマを選ぶ」という価値観が浸透し、EVへの関心も一気に高まりました。
その後も1999年には「ホンダ・インサイト」が登場し、2009年には「三菱・i-MiEV」、「日産・リーフ」など、魅力的なEV車種が次々と生み出されてきました。
そして現在では、EVの普及率はバッテリー技術の進歩や充電設備の整備、政府の補助金制度などの影響を受けて急速に伸びています。
各国で環境政策の一環としてEV普及を促進する取り組みが行われ、EV市場は年々成長しているのです。
電気自動車(EV)の今後の見通しを予測
の普及率は?これまでの歴史と今後の見通し_03-1024x538.png)
「エコカー減税」という言葉が流行語にノミネートされたのも、もう10年以上前のこと。
今では電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)は「流行」ではなく、私たちにとって身近な存在になりました。
EVの技術革新や市場の拡大は急速に進み、今後もさらなる発展が見込まれます。
ここからは、EVの今後の見通しを予測してみましょう。
今後も各国の政府が環境政策に力を入れていく
EVは、世界的な環境課題であるCO2削減の有力な対策として位置づけられています。
これまでに多くの国でEVが推進され、補助金の拡充やメーカーへの規制を推し進めてきました。
しかし、EVの最大市場である中国では、2022年末でEVの補助金政策は終了を迎えました。同様に、EU最大の自動車市場を誇るドイツでも2023年より補助金が削減されるなど、普及速度に一定のストップがかかることが見込まれます。
一方、アメリカでは新たに補助金政策が開始されることになっています。アメリカが認めた国から原材料を調達し、バッテリーの製造と中身の組立までを北米で行ったEVの購入者へ、最大7500ドルの税控除を行うものです。
アメリカの自動車市場の大きさは、中国に続き世界第2位。これほど巨大なマーケット規模だからこそ、この政策はEV推進の大きな力になるに違いありません。
また、2023年2月にフランス東部ストラスブールで開かれたEUの欧州議会では、2035年までにEU地域のガソリン車やディーゼル車の新車販売を禁止する法案が採択されました。
EUでは特に、ガソリンなどの化石燃料を使用する自動車から、EVへと転換する「EVシフト」が加速しています。
一方で、欧州最大の自動車生産国であるドイツをはじめ、イタリアやポルトガル、東欧チェコやポーランドが上記のEU法案の見直しを求めるなど、各国の調整は続いています。
テクノロジーがさらに進化していく
現在、自動車業界は「100年に1度の大変革期」と言われています。
例えばHondaは、「2050年までに全活動のCO2排出量を実質ゼロにする」ことを宣言しました。2040年には四輪のEVとFCVの販売比率を、全世界で100%にすることを目標としています。
世界トップクラスの自動車メーカーを擁する日本だからこそ、今後の技術革新にも大きな期待が寄せられています。
ここでは、モーター、バッテリー、急速充電という3つの視点から近年のEVテクノロジーについてご紹介します。
モーター
2021年に経済産業省が発表した資料によると、EVのモーター分野は主に「効率向上」「小型・軽量化」が早急の課題だとしています。2030年までの「次世代モーター」の開発目標として、85%以上の平均効率や、出力密度の向上などが挙げられています。
また、同時に自動車のモーター市場は、EV・PHEV用モーターをメインに市場が急速に拡大していることに触れ、生産力・価格競争力を高めることが必要だと説いています。
国内の具体的な動きとしては、2021年にリリースされたEV向けのインホイールモーター「Direct Electrified Wheel」が大きな反響を呼びました。
株式会社日立製作所と日立Astemo株式会社が共同開発したこのモーターは、小型化したモーターにインバーターとブレーキを一体化させ、かつ出力密度は世界トップクラスの2.5kW/kgという数字を実現しています。こうした製品が実用化されれば、既存のEV比でエネルギーロスを30%削減し、1度の充電で走行できる航続距離を伸ばすことが期待されています。
バッテリー
EVの普及のカギを握る、次世代電池として注目を浴びているのが「全固体電池」です。
現在のEVで用いられているバッテリーはリチウムイオン電池が主流です。しかし、リチウムイオン電池の改良は限界を迎えており、新たな電池の開発が全世界で行われています。
「全固体電池」は、その名の通り電解質に液体ではなく個体を用いて、電池の軽量化や劣化の低減の実現が期待されている電池です。
2022年6月には、国の研究機関である「物質・材料研究機構(NIMS)」が「全固体電池マテリアルズ・オープンプラットフォーム(MOP)」の本格始動に伴い、記者会見を行いました。
NIMSは、各自動車産業を繋ぐハブ役として、共通した基盤研究を推進することを目的としています。全固体電池の分野においてはトヨタ自動車、デンソー、三菱ケミカル、JFEスチール、村田製作所など、業界のトップメーカーたちが集まりました。
今後は文字通り「オールジャパン」体制で研究が進められ、ノウハウや装置の共有などを経て、激化する世界の開発競争へ打ち勝つことを目指しています。
急速充電
EVの普及の壁となっているのが、充電設備の不足と言われています。
EVは、0から100%充電するのに5~10時間以上はかかるのが一般的です。そのため、出先での「ガス欠」ならぬ「電気欠」を恐れるドライバーも多く、EV購入のネックになっています。
こうした問題を解決するため、急速充電を可能とする充電器を普及させようという動きがあります。
米国シェア1位のテスラは急速充電器であるスーパーチャージャーを、自己負担で世界中に整備しており、それに倣ってポルシェやアウディなどのメーカーも動き出しています。
一方、国内でも株式会社パワーXが自動車の車種やメーカーに左右されない超急速充電器を網羅する事業を開始するなど、新たな動きが広まっています。スマホアプリを通じて利用予約や精算ができる仕組みで、2030年までに国内約7000か所に充電設備を設ける計画です。
また、パナソニックオートモーティブシステムズは、車に搭載できる電動車オンボードチャージャー(OBC)の開発に取り組んでいます。入力電圧800ボルト対応したOBCは、実用可能になれば充電時間をこれまでの半分に短縮できるということもあり、量産が期待されています。
電気自動車(EV)市場が活性化していく
「世界の電動車の新車販売台数に占めるシェアは、2030年には51%にまで伸びる」と、BCG(ボストン コンサルティンググループ)のレポートの中で予想されています。
EVの中でも特に好調なのがバッテリー式電気自動車(BEV)で、欧州では2035年の新車販売の90%以上をBEVが占めるのではないかとされています。
同レポートでは日本市場についても触れられており、日本の電動車の新車販売台数は、2030年には55%を占める見込みがあるとされています。
しかし、日本国内のハイブリッド車のシェア率については、2030年に至ってもほぼ現状維持の23%に留まるだろうという予測がされています。2030年の世界のハイブリッドシェアである7%という推測値に比べ、大幅に後れを取ることが予想されます。
これからの課題
世界的に駆け足で進められているEVシフトですが、国内においてはまだまだ課題が多いと言えます。
一つは急速充電設備の不足です。現状でも休日になると発生している「充電待ち」がさらに増加することになります。また、都心部では充電設備の基数も多いものの、有料駐車場などに設置されたものは利用率が低く、利用回数が偏る傾向にあります。
この問題に関し、NEXCO東日本は公式サイト内にて「NEXCO3会社及びe-Mobility Powerは、EV急速充電器の高出力化・複数口化を推進し、2025年度までに充電口数を約1,100口と大幅に増設する整備見通しを策定いたしました。」と発表しています。2022年度は前年度より82口増設し、2023年度も引き続き155の充電口増設を目指しています。
課題の一つとして、EVの大容量のバッテリーを充電するための電力確保や、車種が限定されてしまうという点も挙げられます。特に後者は車両価格とも密接に関係があり、手の届きやすいEVは数車種に限られてしまうという実態があります。
しかし、軽EV車も登場し「EV元年」を迎えた今だからこそ、今後もさらに選択肢の幅が増えることで、メーカー同士の競争が加速することが期待されます。
まとめ
の普及率は?これまでの歴史と今後の見通し_04-1024x538.png)
電気自動車(EV)は、今後も全世界で普及が続くと予想されます。
また、技術の進歩により航続距離や充電時間の改善が期待され、ますます多くの消費者がEVを選択する可能性が高まっています。
しかし、ただEVへの買い替えを推進するだけでは、本当の意味でEVが普及したとは言えません。
住環境による充電設備の導入の難しさや、新たな電力エネルギー不足の解決など、いわゆる「EVのインフラ」課題を解決することが持続可能なモビリティ社会の実現の第一歩となるでしょう。
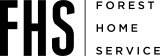
の普及率は?これまでの歴史と今後の見通し_TOP-.png)