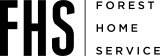近年さまざまなメリットから注目を集めている「V2H(Vehicle to Home)」という言葉をご存じでしょうか。エコカーにおける新たな可能性を秘め、実用化が進むV2Hですが、「詳しくはよく知らない」という人も多いかと思います。
この記事では、V2Hの簡単な概要、仕組み、メリット・デメリットなどを分かりやすく解説します。
V2Hとは?
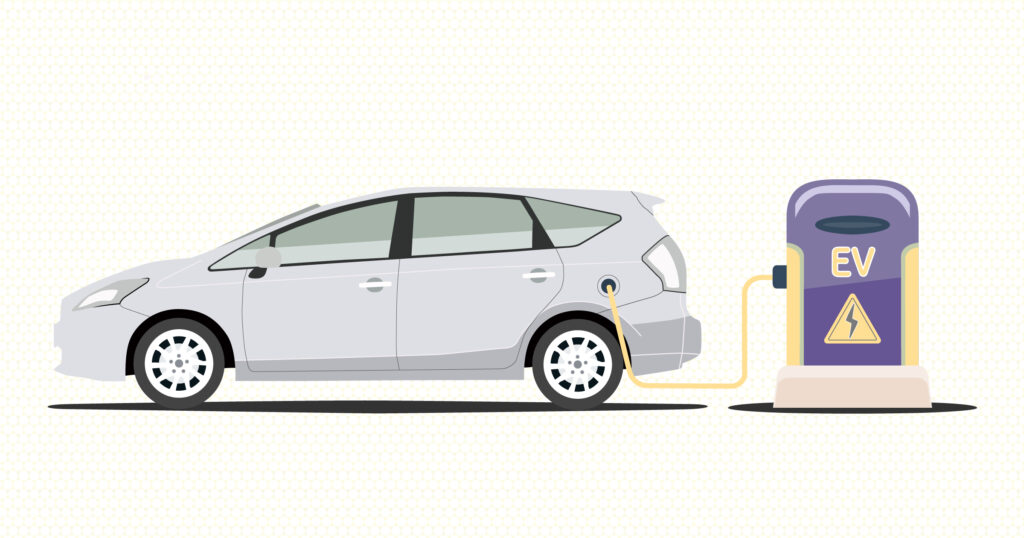
V2H(Vehicle-to-Home)を直訳すると「車から家へ」となります。その名の通り、「電気自動車(EV)のバッテリーを家庭の電力供給に活用する仕組み」を指します。
もともと電気自動車は、ガソリンなどを必要としないエコな移動手段として普及しました。電気自動車の内蔵バッテリーは、数百kmの長距離走行ができる量の電力が蓄えられます。この「大容量の蓄電池」としての機能に着目し、電気自動車が家庭用蓄電池の役割を果たせないかと考えられたのが始まりです。
そこで登場したのが、自動車のバッテリーに充電された電力を家庭用電力へ活用する「V2H機器」です。V2H機器はさまざまなメーカーから、主に2つの種類が出ています。
V2Hは主に2種類

V2Hには「非系統連系」型と「系統連系」型の2つのタイプがあります。設備の形式によって種類や給電の利便性も異なります。ここではそれぞれの違いについて詳しくご紹介します。
「非系統連系」型
V2Hでは、EV・PHVのバッテリーからの電気と、電力会社からの送られる電気、太陽光発電で生み出される電気の3種類を扱うことができます。
「非系統連系」型のV2H機器は、電源が切り替え式になっています。そのため3種類のうち1種類の電気しか使うことができません。また、EVからの電力を使用している間は、太陽光パネルからの給電はできません。同様に電力会社から送られる電気も使用できません。
また、このタイプのV2H機器ではパワコンの出力の関係上、停電時には太陽光発電からEV・PHVへ充電できなくなるため注意が必要です。
「系統連系」型
「系統連系」型のV2H機器は、EVのバッテリーを家庭の電力網に連結し、余剰の電力を供給します。代表的なV2H機器では「電力需給制御システム」という機能がパワコンに搭載されており、EVや太陽光発電、電力会社からの電気を同時に使うことができます。
停電の際には太陽光発電の電力を使用し、EVへの再充電も可能なため、急な災害時も安心です。家庭用蓄電池の場合、停電時に「非常用コンセント」など専用のコンセントからしか電気が使えないケースがあります。しかしながら「系統連系」型はパワコンの出力量が大きいため、通常コンセントで家電を使用できるメリットがあります。
一般的に、ほとんどのV2Hは「系統連系」型を採用しているため、迷ったらこちらのタイプを選ぶのがおすすめです。
V2Hの仕組みと役割を解説

V2H機器は、電気自動車(EV)に充電された電気を家庭で活用するためには欠かせない存在です。一方で、「EVに内蔵された電気も、家庭用電気も同じ『電気』なのに、どうしてV2Hを介さないと使えないのだろう」と思う人もいるのではないでしょうか。
ここではV2Hについての理解を深めるため、その仕組みと役割をご紹介していきます。
家と電気自動車(EV)をつなげる
V2Hには家と電気自動車(EV)をつなげることで、電気自動車のバッテリーを家庭の電力源として使用する役割があります。
電気自動車内に充電された電気は「直流」のため、家庭用に使うには「交流」へと変換する必要があります。V2Hは、こうした電力を家庭で使うために直流から交流へと変換し、家庭で使用できる形で送り出すのです。
もちろん、専用のコンセントを使えば家庭用電力から電気自動車への充電は可能です。しかし、その逆を行うにはV2H機器が必要というわけです。
また、電気自動車に充電された電力は、一家庭の電力を全てまかなえるほどの容量を持ちます。その巨大な電力を変換するためにも、V2H機器が欠かせないのです。
電力会社や太陽光発電の電気を使い分ける
V2H機器は、電力会社や太陽光発電などの外部電源と連携し、電力の使用と供給を柔軟に調整する役割があります。
例えば、昼間に太陽光発電で発電を行っているケースで考えてみましょう。何もしなければ、太陽光発電で作られた電気は、昼間稼働している家電へ優先的に使用されます。しかしV2Hシステムに電気自動車を接続し、そちらを優先的に充電するよう指示すると、電気を電気自動車側へ送ることができます。
雨天などで太陽光による発電ができない場合には、あらかじめ電気自動車に充電してあった電力を家電に送るといった調整も可能です。また、電気自動車の充電分だけではまかなえない場合には、電力会社から送られてくる電力を使用するよう調整します。
こうした細やかな調整は人力で行うには非常に難しく、現実的ではありません。V2Hがあれば、適宜必要なモードへ切り替えることで最も効率の良い電力供給を実現してくれるのです。
V2Hのメリット
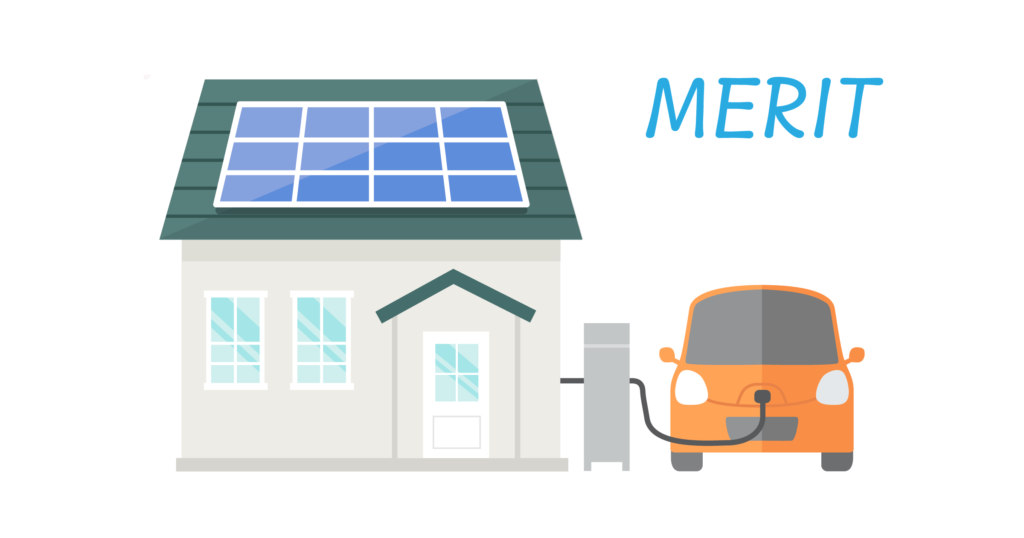
V2Hを活用するメリットは、大きく分けて6つあります。
電気代を節約できる
電気自動車に内蔵されているバッテリーを蓄電池として利用すれば、家庭の電力需要を補うことができるため、電気代の節約につながります。たとえば夜間に電気自動車へ充電しておいた電気を、日中に家電などへ活用する方法などが考えられます。
一般的に、深夜帯に発電される電力は昼間~夕方よりも使用量が低いため、余る傾向にあります。
各電力会社は「深夜電力プラン」(電力会社により名称は異なります)を設定することで、深夜の電気を低価格で提供しています。深夜に充電した電力のみで日中の家庭分をやりくりすれば、大幅な電気代カットが見込めます。
同様に、電気自動車の走行コストも削減が可能です。
すでに太陽光発電を導入しているご家庭であれば、昼間に太陽光で発電した電気を電気自動車へ貯めておき、V2Hを通して家庭用電力として使用することもできます。
蓄電池と比べて電池容量が大きい
電気自動車のバッテリーは一般的な蓄電池より容量が大きいため、多くの電力を供給できます。車種にもよりますが、電気自動車のバッテリーは約10〜100kWhと言われています。一般的な家庭用蓄電池の容量は約4~12kWh程度のため、この差は歴然です。
1人暮らし家庭の1日の電気使用量は6.1kWh、2人暮らしでは10.5kWhと言われています。
普段通りに電気を使っていても「充電切れ」になりにくく、余裕を持てるのが大きなメリットと言えるでしょう。
電気自動車(EV)の充電時間を短縮できる
バッテリー容量にもよりますが、一般的に電気自動車(EV)は長時間充電する必要があります。通常の家庭用200Vコンセントと、15Aの電流を流せる充電設備を使用した場合、40kWhバッテリーの充電には約13.3時間かかります。
しかしながら、急速充電の仕組みを使ったV2H機器であれば、通常の約半分の時間で充電が完了するなど、大幅な時間短縮が可能です。ただし、中にはV2Hに対応していない車種もあるため、購入の際には事前に確認しましょう。
災害時の非常用電源を確保できる
V2Hが注目を集めている理由の一つに、災害時の非常用電源としての用途があります。地震などの災害が多い日本では、停電のリスクも高いため、非常時の電源の確保が重要な課題と言われています。
V2Hは設備さえ無事であれば、停電の際も通常時と同じように電力を使うことができます。そのため、災害対策としても非常に有効です。前述したように家庭用蓄電池より大容量の電力を貯えられるため、長期的な停電時には特に大きな効力を発揮します。
環境にやさしい生活を送れる
日本の電力の約8割は現状、化石燃料による「火力発電」でまかなわれています。日本全体のCO2排出量の約4割は電気事業からのものであるため、いかに火力発電の割合を減らすかが、クリーンな未来のための課題と言えるでしょう。
電気自動車やV2Hが広まった背景には、世界的な「脱炭素化社会」への取り組みがあります。2020年には日本政府も「2050年までの脱炭素化社会の実現」という目標を掲げ、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すと宣言しました。
電気自動車(EV)はガソリンではなく電力を使用することにより、CO2排出量を減らすメリットがあります。しかし、その動力源である電気は火力発電に依存しています。電力会社から供給された電力を使うのは、CO2削減に効果的とは言えません。
V2Hを活用すれば、太陽光発電による再生可能エネルギーの利用の幅が増え、二酸化炭素の排出削減に大きく貢献することができます。自分で使う電気を自分で生み出すという「環境にやさしい生活が送れる」というのも、V2Hならではのメリットです。
補助金をもらえる可能性がある
V2Hの導入には、国や自治体から補助金が出る場合があります。補助金の種類や金額は、お住まいの地域や自治体の制度によって異なるため、V2Hの導入を検討されている場合はまず弊社までお気軽にご連絡ください。
V2Hのデメリット
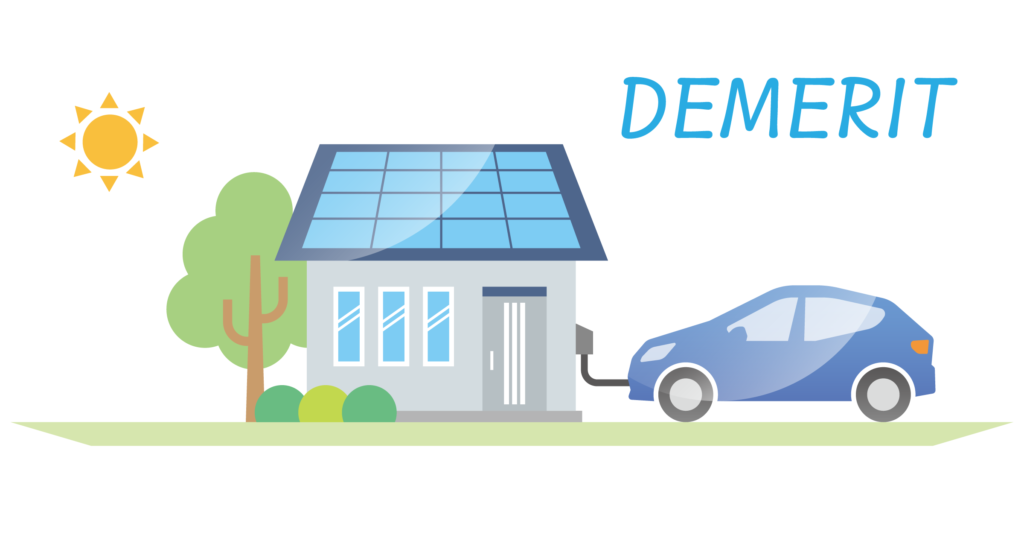
V2Hにはメリットも多くありますが、同時にデメリットもあります。代表的なものを5つご紹介します。
導入にかかる費用が高額
V2Hを導入する上で最大の壁は、高額な初期費用にあります。V2Hシステムの導入には特殊な機器や設備が必要です。例えば電気自動車1つをとっても、多くの場合車両価格はガソリン車より高額となります。
主流となっているV2H機器の本体価格は約50万円~90万円程度ですが、ここに別途設置のための工事費用がかかるのが一般的です。設置費用は戸建ての場合は約30万円以上、マンションの場合は約50万円以上かかるとされています。
一方で、ランニングコストはガソリン車の約半分~3分の1まで削減できます。長い目で見れば費用対効果が高いのが特徴です。そのため、初期費用と節約費用のバランスを考えながら、自分に合った機種を慎重に選ぶことが大切です。
V2H機器の設置場所が限定される
V2Hシステムは「電気自動車と自宅の間」に設置しなくてはなりません。そのため、駐車スペースとの兼ね合いで設置できないというケースも見受けられます。導入の前には、自宅の駐車場やガレージの大きさ、車の大きさ、V2H機器の大きさをあらかじめ考慮する必要があります。
また、V2Hの本体は車の充電口から数メートル以内の場所に設置しなければなりません。スペースの広さだけでなく、位置関係にも注意しておきましょう。
日本では国民の約4割がマンションやアパートなどの共同物件に住んでいます。こうした物件ではV2H機器が新設できないため、多くの人が電気自動車の購入に踏み切れないという実情があります。
経済産業省によると、電気自動車を購入している層は約90%が戸建て住宅に住んでいるというデータが発表されています。「更なるEV・PHV普及のためには、共同住宅への充電設備の設置の促進が必要」ということもあり、国は公共用の充電器の普及と共に、共同住宅への設置も含めたインフラ整備を進めています。
対応車種が限られている
電気自動車はさまざまな車種がありますが、現時点では、V2Hに対応したEVの車種はまだ限られているのが実情です。そのため、V2Hを導入するためには車両の選択に制約がかかります。
代表的なものでは、日産のリーフ、トヨタのプリウス、ホンダのHonda eなどが挙げられます。V2H導入の前には、必ず対応車種をチェックしておきましょう。
電気自動車のバッテリーが劣化する
一般的に、蓄電池は長時間の逆供給や充放電によって、バッテリーの寿命や劣化が進む傾向があります。その性質は電気自動車であっても変わりません。
電気自動車のバッテリーに一般的に使われるリチウムイオン電池は、鉛蓄電池よりも充放電による劣化が少ないのが特徴です。しかし、電気自動車に充電した電気を走行のみに使う場合と比べ、V2H機器を通して家庭用電気として活用した場合では、単純に充電・放電の回数が増えてしまいます。これが、V2Hにより電気自動車のバッテリーが劣化しやすいメカニズムです。
できるだけバッテリーを長持ちさせるには、充電したまま長時間放置し、過充電とならないように気を配る必要があります。
バッテリー充電は30~80%の数字を保ち、定期的な充放電を行うと良いでしょう。
急速充電の多用や高温環境下での使用もバッテリー劣化リスクを高めます。普段から適切な使い方を心がけましょう。
瞬間的な停電が起こる可能性がある
「非系統連携」のV2Hシステムを導入した場合、瞬間的な停電が発生することがあります。
「非系統連携」では、電気自動車(EV)からの給電を行っている間、電力会社からの給電が受けられません。そのため、家庭内で使用している電力量がEVからの給電量を上回ると、自動的に電力会社からの給電に切り替わります。
この時、「瞬断」と呼ばれる瞬間的な停電が生じることがあります。文字通り一瞬の停電のため、ほとんどの家電は影響を受けません。しかしながら、パソコンなど一部の精密機器ではデータが破損する危険性があります。
これらの事象は「系統連携」タイプのV2Hシステムでは起こらないため、購入時に「系統連携」の機器を選ぶことで回避できます。
V2Hでエコで快適な生活を

V2Hは、電気自動車(EVやPHV)のバッテリーを家庭の電力源として活用する仕組みです。充電時間の短縮や電気代の節約、非常用電源としての役割があり、環境問題解決への貢献も期待できます。ただし、導入費用や設置場所、対応車種などの制約もあるため、導入前には十分に確認しましょう。
既にEVやPHVを利用している人はもちろん、今後の購入を検討している人も、本記事の内容を参考にしていただけたら幸いです。
自分の環境に合ったV2Hを導入し、エコで快適な生活を送りましょう。