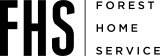電気は私たちの生活に欠かせない存在ですが、日本で発電される電気の約7割は「火力発電」によるものです。環境への影響が懸念される中、今「太陽光発電」が温室効果ガスを削減する取り組みとして注目を集めています。日本政府は2050年のカーボンニュートラル(脱炭素社会)の実現に向けて、太陽光発電とともに家庭用蓄電池の導入も奨励しています。
この記事では、家庭用蓄電池の概要をはじめ、メリットや選び方などをご紹介します。これからのエネルギーライフの新たな選択肢の1つとして、家庭用蓄電池に関する理解を深めましょう。
家庭用蓄電池とは

家庭用蓄電池とは、電力を貯められる装置で、主に家庭での電力消費のために使用されるものです。一般的に、家庭用蓄電池は太陽光発電など、再生可能エネルギーから発生する電気を貯めるために用いられます。
このように、充電して繰り返し使える電池を「二次電池」と呼びます。二次電池の身近な例として、スマートフォンやパソコン、デジタルカメラなどのバッテリーや、電気自動車の車載バッテリーなどが挙げられます。
太陽光パネル単体の導入では、太陽が出ている昼間の発電時にしか電力を使えません。しかし蓄電池とセットで導入すれば、昼の間に充電した電気を蓄電池に貯め、夜間に使えます。
近年では地震や災害に対する意識が高まり、停電時の備えとして蓄電池を導入する家庭も増えています。家庭用蓄電池はさまざまなメーカーから発売されていますが、機能性や蓄電容量などは製品により異なります。それぞれの生活スタイルや住宅の状況に合わせて、適切な蓄電池を選びましょう。
家庭用蓄電池のメリット

太陽光発電システムと併せて家庭用蓄電池を導入すると、さまざまなメリットが得られます。家庭用蓄電池における3つのメリットをご紹介します。
1.電気代を節約できる
昨今、世界的な燃料費の高騰などにより、電気代の値上がりが続いています。こうした背景を受け、家庭用蓄電池が電気代節約に有用なシステムとして注目を集めています。
太陽光発電システムと家庭用蓄電池を組み合わせれば、自宅で発電した電力を直接利用し、余った電力は蓄電池に残すことも可能です。この余剰電力を夜間や雨の日など、太陽光が発電できない時期に使えば、エネルギーの完全自給自足も実現できます。
蓄電池単体の場合でも節約できます。たとえば夜間に電気代が安くなる電気料金プランに加入した上で、夜のうちに蓄電池を充電しておくとします。この蓄えた電気を電気代が高くなる日中に利用すれば、電気代を大幅に節約できます。
蓄電池の中には、電気プランやライフスタイルに合わせて、充電時間や給電時間を設定することも可能なものもあります。
蓄電池を活用すれば、電力会社から電気を購入する頻度も減り、電気代の大幅な節約につなげられます。
太陽光発電システムの導入を検討してる方は、蓄電池も併せて検討すると良いでしょう。
2.停電しても電気機器が使える
近年の日本では、大規模な地震や台風といった自然災害が頻繁に発生しています。災害時には停電が発生することも多く、2011年の東日本大震災では最大466万戸もの家が停電になったと言われています。
もしもの事態に見舞われても、家庭用蓄電池があれば非常用電源として一定時間は電気を使い続けられます。太陽光発電パネルを併設している場合であれば、夜に溜めた電気を使い切ったとしても、天候に恵まれれば翌日の昼間に再充電が可能です。
万が一、停電が長引いた場合でも、冷蔵庫やスマートフォンの充電、照明など、生活に必要な電力をまかなえます。このように、蓄電池は防災の観点からも注目を集めています。
3.電気自動車の動力源になる
ここ数年で一気に普及しつつあるのが、電力を動力とする電気自動車(EV)です。2022年は「EV元年」とも呼ばれ、軽自動車のEVが発売されるなど、販売促進の動きが急速に広まっています。
家庭用蓄電池を活用すれば、日中に太陽光発電から得られた電力を貯め、蓄電分を電気自動車の夜間充電に使用できます。もし日中に通勤などのせいで充電ができなくても、寝ている間に電力がチャージできるのです。
一方で、家庭用蓄電池から電気自動車へ充電する場合、蓄電池の容量や電気自動車の種類によっては十分に充電できない可能性もあります。蓄電池の容量や電気自動車への充電容量、走行範囲などを考慮した上で、適切な運用計画を立てることが重要です。
家庭用蓄電池の種類

家庭用蓄電池にはいくつか種類があります。それぞれの蓄電池は特性が異なるため、使用用途やそれぞれのライフスタイルに合わせて最適なものを選択する必要があります。
ここでは、それぞれの蓄電池の特徴について詳しく見ていきましょう。
鉛蓄電池
鉛蓄電池は、長い歴史を持つ蓄電池の一種で、その信頼性と耐久性の高さから広く採用されています。
鉛蓄電池における特徴として、充電・放電効率が高く、比較的短時間で充電が可能である点が挙げられます。また、繰り返しの放充電に強いため、自動車のバッテリーや非常用電源などにも用いられています。値段も安価なので供給しやすいのも長所です。
一方で、鉛の特性上、鉛蓄電池は重く小型化が難しいデメリットもあります。また、鉛や酸という人体に有害な材料を使用しているため、使用後の処理や廃棄が環境問題になるとも指摘されています。
とはいえ、ZEH住宅(エネルギー収支をゼロにする家)やスマートシティ構想など、大型で容量の大きな蓄電池が求められるシーンは多くあります。サイズが大きくともコストパフォーマンスに優れた鉛蓄電池は、今後も欠かせないものとなるでしょう。
NAS電池
NAS電池は「ナトリウム硫黄電池」とも呼ばれ、その名の通り金属ナトリウムと硫黄を主要な化学物質として構成される蓄電池です。
最大の特徴に、高いエネルギー密度と大容量による長期間のエネルギー保存に適した点が挙げられます。寿命も15年以上と長く、使用サイクル数は4500回と多くの充放電に耐えられます。
風力や太陽光など、変動性のある再生可能エネルギーを効率よく運用するためには、時間帯による需要の変動に対応しなければなりません。その点、NAS電池は一度に大量のエネルギーを蓄えられるため、この変動性をカバーできます。こうした特性からNAS電池は、主に産業用蓄電システムに用いられています。
NAS電池のデメリットは、高温で動作しなければならないことです。ナトリウムと硫黄の化学反応は約300度で発生するため、使用時はヒーターなどによる温めが必要です。こうした点はエネルギー効率を下げるだけでなく、安全性が確立しにくくなります。
リチウムイオン電池
リチウムイオン電池は、リチウムという鉱物を使用した電池です。その軽量性や高いエネルギー密度などの特性から、家庭用蓄電池の中では最もよく使われています。他にも、スマートフォンのバッテリーや電気自動車(EV)など、さまざまな分野で用いられています。
リチウムイオン電池の特徴は、高いエネルギー密度と急速な充放電にあります。また、充電された電力を使いきらない状態で充電を繰り返すことにより、使用可能時間が短くなる「メモリー効果」が起きないのが大きなメリットです。中には一万サイクル以上のものもあり、寿命が長いという利点もあります。
一方で、1kWあたり約20万円という高コストと、高温になると性能が低下する可能性がある点がデメリットとして挙げられます。ですが、現在でも自動車メーカーや電機メーカーによる研究開発が盛んに行われており、使用温度の拡大に向けた改良も進んでいます。
リチウムイオン電池は多彩な用途や電力需要に対応可能なため、多くのケースにおいて最良の選択となり得るでしょう。
ニッケル水素電池
ニッケル水素電池は、「ニッケル」と「水素」という自然界にある2つの素材から作られた電池です。制作過程や廃棄時に有害物質を出すことが少なく、環境に優しいのが特徴です。
リチウムイオン電池の登場以前は、主にモバイルバッテリーなどの携帯機器用の蓄電池として利用されてきました。
コストは1kWあたり10万円とリチウムイオン電池のおよそ半分ですが、過充電や過放電に強く、リチウムイオン同様に急速充電も可能です。使用用途の幅も広く、充電式乾電池であるエネループから、ハイブリッドカーのバッテリーまで、さまざまなニーズを満たせます。
デメリットとしては、自然に電気を放電してしまうこと(自己放電)が多く、寿命も5~7年と短い点が挙げられます。
家庭用蓄電池の選び方

家庭用蓄電池は、さまざまなメーカーから数多くの製品が発売されている分、性能もそれぞれ異なります。
自分の環境に合った蓄電池を選ぶためには、いくつか気を付けるべきポイントがあります。
蓄電池の容量を適切に選ぶ
蓄電池を選ぶ基準には、まず容量が挙げられます。
蓄電池における容量とは、一度に保存できる電力の量のことを指します。蓄電容量が大きな製品を購入しておけば、たくさん電気を使う家庭でも安心して日常を過ごせます。
もし使用電力に対して蓄電池の容量が足りなかった場合、必要な時に電力を供給できないばかりか、充電回数も多くかかります。すると必然的に蓄電池のサイクル回数は増え、寿命が本来よりも短くなる可能性があります。
蓄電池の容量の大きさに比例して、蓄電池の価格も高くなりますので、購入の際は予算と必要な電力量のバランスを十分に考慮しましょう。
バッテリーのサイクル寿命を調べる
バッテリーのサイクル寿命とは、わかりやすく言えば充電・放電できる回数のことです。0%のバッテリーを100%まで充電し、再び0%まで使い切るまでを1サイクルとしてカウントします。
身近な例なら、スマートフォンのバッテリーが想像しやすいでしょう。スマートフォンのバッテリーも、新品時は充電が減りにくく電池の持ちも良いですが、経年による劣化を経ると、電池容量は少しずつ減っていきます。これと同様の現象が家庭用蓄電池にも起こるのです。
例えば、家庭用蓄電池に主に使用されるリチウムイオン電池の平均サイクル数は、6,000~10,000回以上、年数に換算すると約15年~20年と言われています。この数字はあくまでも目安ですので、高温下での使用など、環境によってはさらにバッテリー寿命が早まることもあります。 一般的に、サイクル寿命が長い蓄電池はコストが高い傾向があります。しかし、サイクル寿命の短い蓄電池は頻繁な交換が発生するため、長期的に考えるなら、サイクル寿命の長い蓄電池を選んだ方がコストを削減できるでしょう。
サイズや設置スペースの確保と配線⼯事を考慮する
蓄電池を選ぶ際は機能性だけではなく、設置場所についても検討が必要です。
近年はリチウムイオン電池の台頭により、蓄電池の小型化が進んでいます。また、蓄電池設備そのものも年々小型化しつつあります。とはいえ、蓄電池を置くために一定のスペースを要することに変わりはありません。
家庭用蓄電池は、高温や低温などの急激な温度変化に弱いため、直射日光の当たらない日陰に設置するのが望ましいとされています。加えて、安全上の理由から、水辺や火気のあるところからは遠ざけておきましょう。配線工事まで考慮するなら、分電盤までの距離が短い場所を選ぶことが大切です。
家庭用蓄電池のサイズは、メーカーや品番にもよりますが、ほとんどが100kg~数百kgと重いため、しっかり固定できるかも重要です。 また、蓄電池の設置には、自治体により条例などが定められている場合があります。設置工事の前には、制約がないか事前に確認しておきましょう。
ブランドやメーカーの信頼性を確認する
一度購入した家庭用蓄電池は、その後長期にわたって使用し続けることになります。そのため、定期的なメンテナンスやサポートが必要です。運用中、蓄電池に故障やトラブルが発生したときに、迅速に解決してくれるメーカーを選ぶのが大切です。
信頼性の高いメーカーの製品を選ぶことで、保証だけでなく精神的な安心感も得られるでしょう。
また、製品の強度や壊れにくさといった製品の安全性も気になるポイントです。メーカーによっては製造工程や設計段階で厳しい評価基準を設けている会社もあります。
目先の安さではなく、「この先も長く使い続けられるメーカーか」という基準で選ぶことが重要です。保証内容や保証期間、アフターサービスの内容などはメーカーにより異なりますので、必ず確認してください。
価格やランニングコスト
「電気代の支出を抑えるために家庭用蓄電池を導入したい」という人が考えなくてはならないのが、蓄電池の価格(イニシャルコスト)とランニングコストです。
イニシャルコストは「初期費用」のことです。一方、ランニングコストは「運転資金」や「設備を維持するための費用」、「維持費」を指します。
蓄電池を導入する際にかかるイニシャルコストとしては、蓄電池の本体価格に加え、パワーコンディショナー(パワコン)の機器本体費用、設置工事費、電気工事費などが挙げられます。設置費用については、設置する場所が屋内・屋外か、あるいは蓄電池の重さはどれくらいかといったさまざまな条件により変動します。
ランニングコストであれば、実のところ蓄電池そのものにはそれほど多額の費用はかかりません。ですが、もしも太陽光発電と併用する場合は、FIT法による定期的なメンテナンスが推奨されています。安定的に発電するためにも、定期的な清掃コストなどを含めたメンテナンスコストは考えておきましょう。
導入方法によっては、イニシャルコストが高くランニングコストがそれほどかからないケースや、あるいはその逆もあります。目の前の本体価格の安さに振り回されず、長期的な視点で購入を考えましょう。
家庭用蓄電池は、時期によっては地方や国が補助金を給付している場合があります。補助金制度をうまく活用できれば、初期費用を大きく抑え、お得に蓄電池を導入できます。
信頼できる業者を選ぶ
蓄電池を購入する際には、信頼できる業者選びが非常に重要です。
購入先としては、ハウスメーカー、家電量販店、訪問販売などがありますが、それぞれに注意点があります。
ハウスメーカーは、下請け業者に外注する場合が多く、その結果、費用が高くなることがあります。家電量販店は、一般的に電気全般の知識を持っているものの、蓄電池の設置や配線については専門外であることがあります。また、ネットでの購入は価格が魅力的ですが、設置や配線の面でのサポートが不足することがあり、特に安全面でのリスクが心配です。
そのため、蓄電池を安心して使用するためには、専門的な知識と経験を持ち、安全で信頼性の高いサービスを提供する専門店に依頼するのがベストな選択です。専門店ならではのサポートを受けることで、長期的に安心して蓄電池を使用することができます。
業者選びの際には、過去の実績や口コミ、アフターサービスの充実度なども考慮し、信頼できる専門業者を見つけましょう。
家庭用蓄電池の今後

テクノロジーの進歩により、家庭用蓄電池の蓄電量や寿命、効率性などの性能は年々向上しています。昨今では、家庭用蓄電池を家電や照明などに自家消費するだけでなく、電気自動車(EV)など車載用バッテリーとして使う例もあります。
経済産業省の発表によると、当面はEV市場の拡大に伴い、車載用蓄電池市場が急拡大するとされています。加えて定置用蓄電池市場も、2050年の脱炭素社会の実現に向けた成長を見込んでいます。
今後に向けて、政府では蓄電池や材料を国内製造するための基盤の確立や、蓄電システムの海外展開、人材育成などの戦略が立てられています。また、具体的な数値目標として、遅くとも2030年までに蓄電池および材料の国内製造基盤を150GWh/年にするとしています。
家庭用蓄電池の需要は、こうした政府の後押しや再生可能エネルギーの普及により増加傾向にあります。蓄電池を導入する家庭数が増えることで、自己消費型のエネルギーシステムが構築できるかもしれません。
昨今の物価高騰の流れで、蓄電池もどんどん価格が上がっていくことが予想されるため、早めの導入がおすすめです。
おわりに

JPEA(一般社団法人太陽光発電協会)が想定した「2050年エネルギー消費」によれば、徹底的な省エネと電化によりエネルギー消費量は半減する一方で、電力需要はますます増加するとされています。
環境問題やエネルギー問題の解決には、太陽光発電などの持続可能なエネルギー源への移行が欠かせません。家庭用蓄電池は、エネルギーの自給自足や停電対策などを通して、さまざまな課題を解決する希望とみられています。今後の技術革新や蓄電池の普及に注目が集まっています。